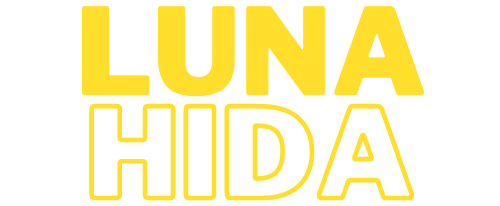第二次マンガ革命史 劇画と青年コミックの誕生【電子書籍】[ 中川右介 ]
第二次マンガ革命史 劇画と青年コミックの誕生【電子書籍】[ 中川右介 ] ショップ:楽天Kobo電子書籍ストア
価格:2,420 円
|
戦後、それまでの「漫画」は、手塚治虫による「ストーリーマンガ」の登場により、まったく別のものになった。
これを仮に「第一次マンガ革命」と呼ぶ。
従来の風刺画・滑稽画から始まった「漫画」と、手塚の「ストーリーマンガ」とは、「コマ」があること、「ふきだしの中にセリフが書かれている」という共通点はあるが、「物語」の有無において根本的に異なっていた。
戦前からの「漫画」を引きずりながら、戦後の「マンガ」は新たな文藝ジャンルとして発展していった。
手塚マンガは多くの亜流を生み、テレビアニメとも連動して、巨大産業へと成長した。
だが、やがて「手塚マンガは古い」とする勢力が現れた。
彼らは自分たちの描くマンガを、手塚治虫とその影響下にあるマンガと区別するために「劇画」と呼んだ。
「劇画」が登場したのは貸本屋向けのマンガにおいである。
一九五〇年代の日本は、まだ本や雑誌を買える人が限られていたので、貸本屋が隆盛だった。
貸本マンガの読者は子どもだけでなく、中卒・高卒で働いている若い労働者も大衆小説と同じように読んでいた。
しかし、すでに中学生ではない彼らは、マンガを好んではいたが、「子どもっぽい」と物足りなく感じていた。
描き手のマンガ家たちも子ども相手のマンガに物足りなくなっていたーーここに需要サイドと供給サイドの思いが一致し、青年を読者に想定したマンガが生まれた。
その青年向けマンガの描き手が、自分たちの描くものは「劇画」だと宣言したのが、一九五九年である。
そしてこの同じ年、小学館は「週刊少年サンデー」を、講談社は「週刊少年マガジン」を創刊し、両誌ともマンガを柱とした。
月刊の少年誌・少女誌もマンガが柱となっており、少年マンガ・少女マンガは隆盛を迎えていた。
それにともない、一九六〇年代も半ばになると、貸本マンガ業界が衰退していく。
ごくわずかの貸本マンガの描き手だけが、一般書店で販売される雑誌へ転身できた。
その代表が白土三平や水木しげるだった。
彼らを積極的に受け入れたのが、手塚治虫と絶縁した「週刊少年マガジン」で、少年誌でありながら劇画の牙城となっていく。
白土と水木の二人を柱にして、一九六四年に「ガロ」が創刊された。
新人の発掘にも熱心で、実験的・前衛的なマンガがこの雑誌から生まれていく。
「ガロ」に刺激されて、一九六六年に手塚治虫が創刊したのが、「COM」だった。
この雑誌からも多くの新人が巣立っていく。
一方、青年がマンガを読むと知った出版社は、「青年コミック」という新たな市場を開拓した。
一九六六年に「コミックmagazine」(芳文社)が最初の青年マンガ誌として創刊され、六七年に「週刊漫画アクション」(双葉社)と「月刊ヤングコミック」(少年画報社)、六八年に「ビッグコミック」(小学館)、「プレイコミック」(秋田書店)と次々と青年コミック誌が創刊された。
「劇画」はこの新市場にも流れ込んだ。
手塚治虫の革命が第一の革命ならば、「劇画」は第二の革命の始まりだった。
やがて「青年マンガ」「青年コミック」が市民権を得て第二次マンガ革命は成就する。
(「はじめに」より抜粋)
画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。
※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。
※このページからは注文できません。
ショップ:楽天Kobo電子書籍ストア
価格:2,420 円
|
0 (0件)